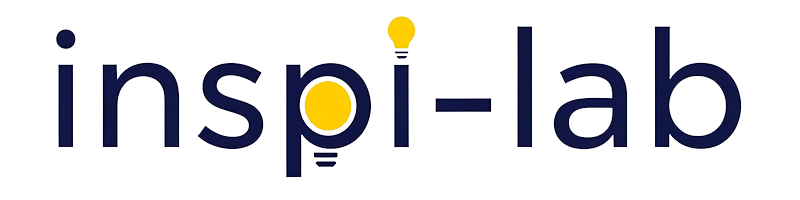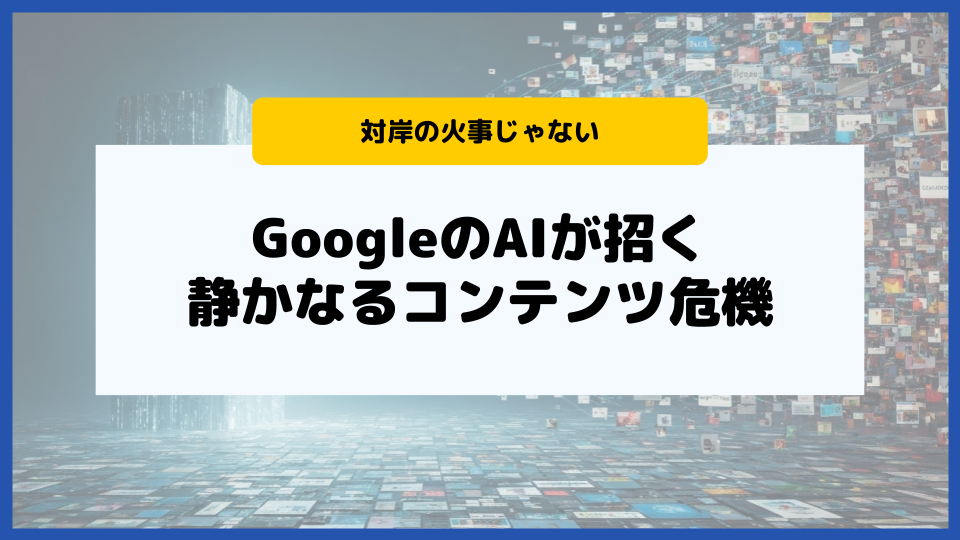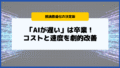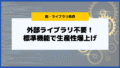Googleは「悪徳事業者」? 問題の核心に迫る
なぜ、巨大テック企業のGoogleが「悪徳」とまで呼ばれてしまうのでしょうか。問題の根源は、Googleが採用している、ある巧妙な戦略にあります。
逃げ道なしの「究極の二択」
Googleは、「Googlebot」というプログラムを使ってインターネット上の情報を集め、検索結果に表示しています。これは、ウェブサイト運営者(パブリッシャー)にとって、読者を呼び込むための生命線です。
しかし問題は、Googleがこの全く同じ「Googlebot」を使って、検索結果に表示するAIの回答(AI Overview)のための情報も収集している点です。AIがサイトの内容を要約してしまうため、ユーザーはわざわざ元のサイトを訪れる必要がなくなり、結果的にパブリッシャーへのアクセスが激減してしまいます。
ここでパブリッシャーは、絶望的な二択を迫られます。
- 選択肢A:AIにコンテンツを使われるのを黙って受け入れる。(アクセス激減のリスク)
- 選択肢B:AIに情報を渡さないよう「Googlebot」をブロックする。
一見、Bを選べばよさそうですが、そうするとAIだけでなく、通常のGoogle検索の結果からもサイトが完全に消えてしまうのです。これは、ビジネスの死を意味します。つまり、パブリッシャーには実質的に「ノー」と言う権利がなく、Googleにコンテンツを差し出すことを強制されているのが現状なのです。
見せかけの対策? Googleの巧妙なワナ
もちろん、Googleも批判を黙って聞いているわけではありません。「Google-Extended」という仕組みを用意し、「これを設定すれば、AIにコンテンツを使わせないようにできますよ」と説明しています。
しかし、これが非常に巧妙な「おとり商法」だと指摘されています。なぜなら、この設定でブロックできるのは、あくまでGoogleの将来のAIモデルの「学習」にデータが使われることだけだからです。
パブリッシャーのアクセスを今まさに奪っている、検索結果の「AI Overview」での利用は、この設定では一切防ぐことができません。Googleは、パブリッシャーに「選択権を与えている」という体裁を整えつつ、最も重要な部分ではコンテンツを利用し続ける仕組みを作り上げているのです。
ウェブサイトから人が消える。「ゼロクリック検索」の恐怖
GoogleのAI戦略がもたらす最も深刻な影響は、「ゼロクリック検索」の増加です。ユーザーはAIの要約を読んで満足し、元のウェブサイトへのリンクをクリックしなくなる。この現象は、すでに壊滅的な被害を生み出しています。
- ある調査では、米国の主要メディアサイトで、Google検索からのアクセスが中央値で10%も減少。エンタメ系のサイトでは14%もの落ち込みを記録しました。
- 一部のサイトでは、最大で25%ものトラフィックを失ったと報告されています。
- ファッション誌などを発行するPenske Mediaは、AI Overviewのせいでアフィリエイト収益が3分の1以上も減少したとして、Googleを提訴するに至りました。
これは、単にサイトのアクセス数が減るという話ではありません。私たちが無料で質の高い情報を得られるのは、サイト運営者が広告収入やサブスクリプションで収益を得て、コンテンツ制作に再投資しているからです。その収益源が断たれれば、良質なコンテンツは作られなくなり、最終的にはインターネット全体が質の低い情報で溢れかえる「情報の砂漠化」につながりかねません。
Googleだけじゃない! AI業界の「勢力図」はどうなってる?
興味深いのは、AI業界のすべての企業がGoogleと同じような強硬策をとっているわけではない、という点です。むしろ、Googleのライバルたちは正反対の戦略で支持を集めようとしています。
協調路線のライバルたち:「善良な事業者」OpenAI
ChatGPTを開発したOpenAIは、パブリッシャーと積極的にパートナーシップを結び、コンテンツの利用料を支払う戦略をとっています。AP通信、フィナンシャル・タイムズといった世界の名だたるメディア企業と契約を結んでいます。
皮肉なことに、Googleを「悪徳事業者」と非難したCEOのニール・フォーゲル氏も、OpenAIのことは「善良な事業者(good actor)」と評価しており、その姿勢の違いは業界内で明確に認識されています。
他にも、AI検索エンジンのPerplexity AIは、AIがコンテンツを利用した頻度に応じて収益を分配する「レベニューシェアモデル」を提案するなど、Googleとは異なるエコシステムを築こうとする動きが活発化しています。
市場は、「検索の独占力にものを言わせるGoogle」と「対価を支払ってでも高品質なデータを確保したい挑戦者たち」という構図で二極化しつつあるのです。
世界が動く!法律とルールでGoogleを包囲
この問題は、法廷や各国の規制当局をも巻き込む大きなうねりとなっています。
アメリカでは、AI企業に対する著作権侵害訴訟が相次いでいます。まだ司法判断は定まっていませんが、「AIの出力が元のコンテンツと競合する場合、フェアユース(公正な利用)とは言えない」という判例も出てきており、AI企業にとって予断を許さない状況です。
一方、より大きなインパクトを持つのが、EUの「AI法」です。この法律は、AI企業に対し、コンテンツ制作者が拒否権(オプトアウト)を示した場合、そのデータをAIの学習に使うことを禁じています。さらに、学習に使ったコンテンツの要約を開示する義務も課しており、透明性を高めようとしています。
最も重要なのは、このEUのルールが「EU域外にも適用される」という点です。つまり、世界中でビジネスを展開するGoogleは、EUの厳格なルールを無視できなくなる可能性が高いのです。シリコンバレーの「Move fast and break things(素早く行動し、破壊せよ)」という文化は、法という大きな壁に直面しています。
まとめ:情報の未来は誰の手に? 持続不可能なGoogleの戦略
ここまで見てきたように、Googleがパブリッシャーのコンテンツを無償で利用し続けるという現在の戦略は、もはや持続不可能と言えるでしょう。
- 法的圧力:アメリカでの高額な賠償金のリスク。
- 規制の圧力:グローバル基準になりつつあるEU AI法。
- 競争上の圧力:対価を支払うライバル企業への信頼とデータの集中。
これら「三つの包囲網」により、Googleは戦略の転換を迫られる可能性が極めて高い状況です。
一方、パブリッシャー側もただ手をこまねいているわけではありません。Googleへの依存度を下げ、ニュースレターやアプリを通じて読者と直接繋がる努力をしたり、AIからの情報収集を技術的にブロックして交渉のテーブルに着かせたり と、生き残りをかけた戦いを始めています。
この対立の行く末は、単にテック業界の地図を塗り替えるだけでなく、私たちがどんな情報を、どのような形で手に入れることになるのかという、社会の根幹を左右します。AIがもたらす利便性の裏側で進むこの「静かなる危機」に、私たちはもっと関心を持つべきなのかもしれません。